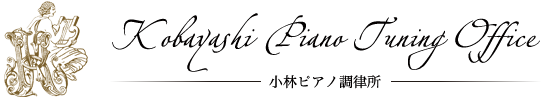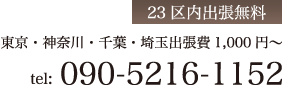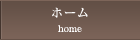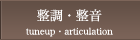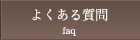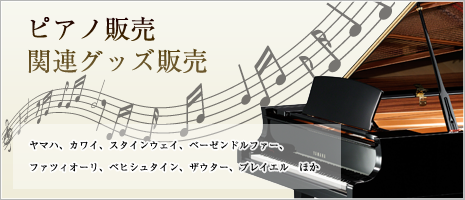CFⅡ
『草枕』は、住みにくい人の世を芸術の力で打破できぬかと思案する青年画家の話ですが、古風な東洋趣味の小説というよりも、奇妙な小説。
『草枕』が書かれた明治39年は日本のピアノが誕生した頃で、山葉寅楠がアメリカにいった7年後くらい。
ピアノつくりはひたすら欧米の文物を学ぶことだったと思いますが、漱石は西欧的思考の根源的な矛盾を発見した最初の日本人。
『草枕』は普通の文学とは違って、何かを表現するというではなく、たんに多彩な言葉で織られた文章。「智に働けば角がたつ。情に棹せば流される。」の意味を探すべきではないのこと。
グールドは、コンピューターに優るエレクトリック・マシ-ンとご自慢のヤマハCFⅡで『ゴルトベルク変奏曲』再録音やブラームス『バラードとラプソディー』などを録音。
優れたエレクトリック・マシーンCFⅡでの録音は、どことなく人情があるかのように聴こえる演奏ですが、逆にそれ以前のスタインウェイでの録音はどちらかというと、ひたすら多彩な音で織られた「非人情」の演奏ように個人的には聴こえます。
「物は見様でどうにもなる、音はどうとも聞かれる、余裕のある第三者の地位に立てば面白い」です。
浜松
東京アラートが解除されることを願っておりますが、自粛中には多くの録りためたTVを視聴。中でも今年始め頃のブラタモリ、なぜ浜松が楽器の町になった♪が、とてもよかったです。
徳川家康が東の武田信玄に対抗して浜松に城を建てる。洪水が起こりやすい天竜川では綿花栽培が適していた。織物をするようになり織機をつくる木工職人が集まる。織機とオルガンはペダルの感じがどことなく似ている。明治維新後にオルガンが来て、故障したオルガン修理に成功した山葉寅楠はピアノつくりを目指すようになりアメリカに5か月の見学。
TVに米ピアノ会社名は出ませんでしたが、キンボール、メイソン・アンド・ハムリン、スタインウェイ・アンド・サンズなど視察したようです。
かつて浜松は木材の一大集積地で南アルプスから天竜川で運んだ。
楽器用木材の乾燥には遠州の空っ風が適していた。
旧軍時代、飛行機のプロペラは木製で日本楽器製、つまりピアノの木工技術で作られていた。
やがて金属製プロペラになり、その金属加工技術は管楽器に活かされていく。
との話が45分に凝縮されていました。
ともすると部分的に小難しくし過ぎてしまうのではなく、大きな流れをわかりやすく、ざっくりと捉えていくことがとても大切であると感銘いたしました。
For here, or to go ?
徳川幕府の鎖国により江戸が繁栄し、菅原道真公が遣唐使を廃止することで平安文化が花開いた。
東京オリンピックで外に向かって開こうとしていますが、外に開いた後には内向きになってくるのがパターンな様に見えます。
オリンピックバブルの後は景気は後退していくとも聞こえてきます。
パーソナリティーには外向型と内向型があるとのこと。
自分の外に正しいものや価値があると感じやすい人が外向型、自分の内にあると思う人は内向型。
明るい暗い、社交的か引っ込み思案とかとは別の分け方。
興味深い話ですが、個人パーソナリティーみたいなものが国や民族にもあるのかどうかを知りたいところです。
日本は外国の物マネが得意な反面、独自に進化させるのが得意ですが、
古来から日本は大きくは2つの異なる共同体があって、そのせめぎ合いで発展したとの説もあります。
オリンピック後、閉鎖的になり不景気になるようで、もしかしたら新しい時代が来ると思うのは楽観的すぎるのかどうか、わかりません。
ピアノは日本人にとって欧米モノマネ文化だとは思いますが、まだまだ独自に発展していくことを願っております。