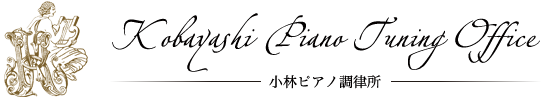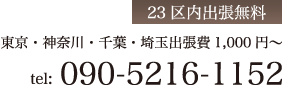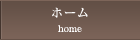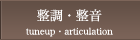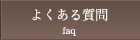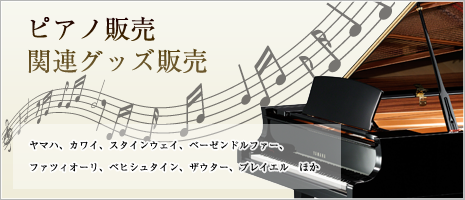テンペラメント
調性というと私は、バッハのウェルテンペラメントやショパン、スクリャビン、ショスタコーヴィチ、ラフマニノフの24プレリュードなどを思い浮かべます。
バッハは、ハ長→ハ短→嬰ハ長→嬰ハ短→二長→二短→変ホ長→変ホ短→ホ長→ホ短~、同主調×半音階の順。
嬰ハ長は音楽史上初使用の曲らしい。
ショパン、スクリャビン、ショスタコーヴィチは平行調×属調の順。
嬰ハ長と嬰二短は無いようです。
ショパンとショスタコーヴィチは嬰へ長ありで変ト長なし。
前半13曲が♯系で後半11曲が♭系。
スクリャビンとラフマニノフは嬰へ長なしで変ト長ありなので、前半12曲後半12曲。
♯系は弦楽器的、♭系は管楽器的でしょうか。
♯系は外交的、♭系は内向的な感じが私はします。
また、♯系と♭系の調号数と長短が同じだと似ているような気がします。
私はいつまでたっても全然弾けないショパン24を弾いてみてはいるので、調性イメージの中心にあります。
ラフマニノフ24は聴くだけですが、調性順ランダムのようです。
勝手にイメージトレーニングしてみました。
1:嬰ハ短 月の幻影
2:嬰へ短 夜の帳がおりる
3:変ロ長 天空を舞う
4: 二短 死の予感
5: 二長 祝祭
6: ト短 悲しい思い出
7:変ホ長 あふれる喜び
8: ハ短 事件
9:変イ長 希望のめばえ
10:変ホ短 迷い
11:変ト長 おどけた黄昏
12: ハ長 真っ白な荘厳と解放
13:変ロ短 迫る不安
14: ホ長 牧歌的
15: ホ短 ただよう哀愁
16: ト長 春のおとずれ
17: ヘ短 重苦しい
18: ヘ長 きらめく星々
19: イ短 妖しい陰り
20: イ長 幸せのはじまり
21: ロ短 孤独な戸惑い
22: ロ長 愛の悦び
23:嬰ト短 焦燥と動揺
24:変二長 霧のノスタルジア
古典調律は平均律と比べて調性の違いがハッキリすると聞きますが、まずは音楽的な調性の違いや味わいを実感するところからスタートしたいです。
参考図書 『調性で読み解くクラシック』
美しい空虚
京都に住み、睡眠薬濫用で危ういときに執筆された『古都』は旅行前に読んでおくべきでした。
絶望的な状況の夢想は明晰で、限りなく優美に燦爛する。
ダイアローグに物語る谷崎にくらべ、モノローグで和歌的な川端。
最近、「The Real Chopin」という古楽器による全集を聴きました。
ダイアローグなベートーヴェン?よりモノローグなショパン?の方がピリオド楽器の、音圧なく濁らず透明な響きに合うように思いました。
どうにもならないときの作品ほど。
「傍に眠っていましたとき、あなたの夢をみたことはありませんでした」
作品と状況は残酷に対比する、愛と悲劇も。
鉄とステンレス
太陽や他の天体にも豊富にあり、地球の地殻の約5%を占める鉄。
男の料理好きなら、一度は中華鍋を手にしたがる人が多いかと思います。
私も若い頃に、わざわざ購入して遊びました。
最近は、ステンレスのフライパンが健康に良いとの話を聞き使ってみましたが、やたらと引っ付く。
とてもじゃないが使えないと思って調べてみたら、中華鍋と同じで空焼きしてからが基本。
それを知ってからは使いやすくなり、かなりの優れもの!専ら使用しています。
熱処理といえば、スタインウェイの鉄骨は他メーカーと比べて低音の鋳物なので、錆びやすいが音は良いと聞きます。
チューニングハンマーでは、シャフト部を鉄とステンレスで比較してみました。
鉄は叩けばキーンと鳴りますがステンレスは鳴らない。それが調律にも影響して、かなり微妙ですが華やかな音になる印象が私にはありました。材質の違いを人が敏感に感知して、そう調律するのかもしれません。
印象論だけでなく、物理的に音質測定してみたいものですが。
それにしても料理と楽器、音楽は近いところにありそうです。