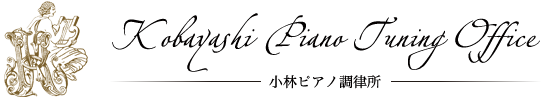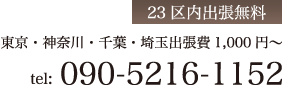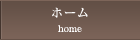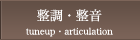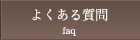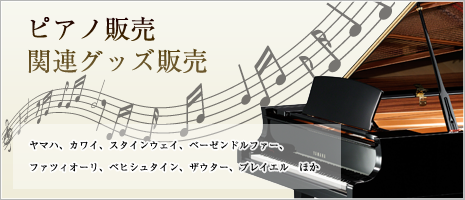ピアノの平均律
a1=440と言うものの、実際の調律音程をつくるには、a1ではなくa=220から始めます。
大抵の人はf-e1間でつくると思います。
私はa-d1-g-c1-f-b-dis1-gis-cis1-fis-h-e1の順にやります。
まず、a-d1間の4度ですが、純正4度は4:3の比率なので、
aの4倍音がa2=880
平均律だとd1=293.67
a2=293.67×3=881.01
881.01-880=1.01
1秒間に1.01のウナリが出るということです。
ここまでなら、それほど難しくない計算で済むのですが、インハーモニスティーが絡んでくるので、実際はややこしくなります。
a=220、弦長773㎜、弦直径1.025㎜とするなら、
3.3×10の15乗×1.025の2乗÷773の4乗÷220の2乗=0.2006311365セントが第1倍音のインハモ。
aの第4倍音を計算するには、
2×4の2乗=32
0.20×32の平方根=1.13137085セントが第4倍音のインハモ。
220×4×2の1200乗根の1.13137085乗=880.5752727
a2=880.5752727ヘルツ。
平均律d1=293.67、弦長594㎜、弦直径1.000㎜とするなら、
3.3×10の15乗×1.0の2乗÷594の4乗÷293.67の2乗=0.30761164セントがd1第1倍音のインハモ。
d1の第3倍音は、
2×3の2乗=18
第1倍音インハモ0.30×18の平方根=1.272792206セントがd1第3倍音のインハモ。
293.67×3×2の1200乗根の1.272792206乗=881.6579511
a2=881.6579511ヘルツ
881.6579511-880.5752727=1.0826784ヘルツ
インハーモニスティーを考慮したa-d1間は、
1秒間に1.08のウナリが出るということでした。
インハーモニスティー
ピアノ技術者ならインハーモニスティーのことは周知のようにみえますが、計算式は難しく、更に値はセント値になります。
セント値は多少性能いいデジタルチューナーで出てきますが、ヘルツに換算するやり方は理解されていなように思います。
以前にも書いたのですが、割り算であるはずがないのです。
オクターブ1200セントで平均律半音間100セントであるなら、
(880-440)÷1200=0.366
平均律a=440で、h=466.16。
(466.16-440)÷100=0.2616
すでに矛盾しています。
やはり、2の1200乗根と考えるのが正しいかと私は思います。
2の12乗根の更に100乗根と値が一致します。
インハーモニスティーの計算は、弦の材質からくる値3.3×10の15乗×弦直径の2乗÷弦長の4乗÷周波数ヘルツの2乗。
出てきた値はセント値。
よくあるのが440ヘルツ、弦長412㎜、弦直径0.975㎜。
3.3×10の15乗×0.975÷412の4乗÷440の2乗=0.5767987871セント。
この値は第1倍音のインハーモニスティーです。
それでは、第2倍音のインハーモニスティーはというと、8の平方根を掛けるという。
オクターブは周波数×2。
インハーモニスティーは2の2乗なので2×4で8とのこと。
0.5767987871×8の平方根=1.631433335
インハモを考慮した第1倍音のピッチは、
440×2の1200乗根の0.5767987871乗=440.1448916
a=440.1448916ヘルツとします。
インハモを考慮した第2倍音のピッチは、
880×2の1200乗根の1.631433335乗=880.8296614
a1=880.8296614ヘルツ。
880.8296614-440.1448916×2=0.5398781609
aの1音だけで、第1倍音と第2倍音の差が0.539ヘルツもありました。
和音どころか、1音だけで既にインハーモニ―ということです。
周波数
近頃、ソルフェジオ周波数というのを見かけます。
1939年ロンドン国際会議による標準ピッチはすっかり悪者扱いで、良い周波数(ヘルツ)があるとのこと。
174安定、285促進、396解放、417変化、528DNA修復、639調和、741自由、852直観。
音階になりそうなのは、174へ、396ト、417嬰ト、528ハ、741嬰へ。
平均律a1ピッチにするなら、
174→438.44 396→444.49 417→441.79 528→443.99 741→440.59
全体に440以上のピッチです。
444に調律すると心地よいとの話もあるようですが、ピアノの場合は弦切れが心配です。
実際現場では、アコースティック楽器合わせだと弦切れしないよう、440指定もそれなりに多くあります。
また、少数点以下のピッチを計算上出しても、実際には温湿度変化や日光や照明が当たったりすれば、コンマ以下はすぐに変化しますし、インハーモニスティの計算は複雑化するので除外しています。
医療上?には音叉を使ったりするようですが、どこまで正確な周波数でなければならないかもわかりません。
ちなみに音叉を調律に使う人もいますが、温度変化の影響を受けやすいので、基音はデジタルチューナーなどでとるほうが正確であるとの見解が増えつつあるかと思います。
デジタル思考的なもので、ピッチ変化しやすいアコースティックな楽器にあてはめていくのは、あまり向かないように私は思いました。