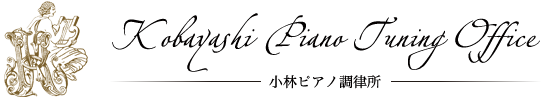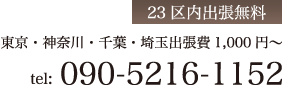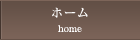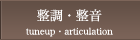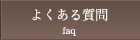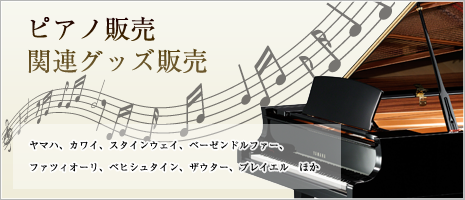Home > ブログ
調律ルネサンス
ローマ・カトリックに対する反抗がルネサンスを生みました。
音楽史ではバッハの死んだ年である1750年を境にバロックからクラシック期になると言われています。
ピアノはクラシック期以降の音楽と関係が深いです。
西欧でクラシックと言うと、古代ギリシャ・ローマを暗示しているようです。
バロック期の音楽は幾何学模様のように抽象的でストイックに精神浄化します。
対してクラシック期は具象的です。古代ギリシャに由来する倍音律を復活させた和音は感情にシンクロし、そこに旋律をつけ、人間的な喜怒哀楽を開放する音楽になってきます。
このあたり、調律にも関係する話だと思います。
今の調律師は平均律で調律するのが一般的ですが、調律師によってオクターブの拡げる幅が微妙に差があったりします。
簡単にざっと言ってしまえば、オクターブ拡めなら派手目な開放感があり、オクターブ純正気味なら端正な感じになります。
ピアノの置かれる場所がホールなのか家庭なのか?ピアノコンチェルトやソロ、反対に伴奏に使用するのか?
更に、どのような時代の音楽を演奏するのか?
によっても適正が変わります。
調律師の好みや性格も関係します。
しかし調律師がいろいろと調律のやり方を変えたところで、結局はその調律師の音がするという説はあります。
オクターブの拡げ方だけでなく、単音でも調律師によって音の違いがあります。
ピアノは一音につき弦は3~1本ですが、調律が合っていても音は違います。
ピアノの音は減衰音だから違いが出る、という話もあります。
音楽史ではバッハの死んだ年である1750年を境にバロックからクラシック期になると言われています。
ピアノはクラシック期以降の音楽と関係が深いです。
西欧でクラシックと言うと、古代ギリシャ・ローマを暗示しているようです。
バロック期の音楽は幾何学模様のように抽象的でストイックに精神浄化します。
対してクラシック期は具象的です。古代ギリシャに由来する倍音律を復活させた和音は感情にシンクロし、そこに旋律をつけ、人間的な喜怒哀楽を開放する音楽になってきます。
このあたり、調律にも関係する話だと思います。
今の調律師は平均律で調律するのが一般的ですが、調律師によってオクターブの拡げる幅が微妙に差があったりします。
簡単にざっと言ってしまえば、オクターブ拡めなら派手目な開放感があり、オクターブ純正気味なら端正な感じになります。
ピアノの置かれる場所がホールなのか家庭なのか?ピアノコンチェルトやソロ、反対に伴奏に使用するのか?
更に、どのような時代の音楽を演奏するのか?
によっても適正が変わります。
調律師の好みや性格も関係します。
しかし調律師がいろいろと調律のやり方を変えたところで、結局はその調律師の音がするという説はあります。
オクターブの拡げ方だけでなく、単音でも調律師によって音の違いがあります。
ピアノは一音につき弦は3~1本ですが、調律が合っていても音は違います。
ピアノの音は減衰音だから違いが出る、という話もあります。

高橋名人と『夜のガスパール』
テレビ朝日の「しくじり先生 俺みたいになるな」が好きで、わりと観ています。
今回は高橋名人が出演されてました。
私はインベーダー世代で小学生時代によく遊びました。
高橋名人は当時、有名人でしたが、実はゲームが下手だったとのことでした。
ただ秒間16連打というのはウソではないようで、なかなかマネできないように思います。
ラヴェルの「夜のガスパール」のスカルボに、dis音を約217回連続連打的な難曲があります。
親指、人差し指、中指の3本の指を使って弾くことが多いようですが、人差し指1本だけで弾く方もいらっしゃいます。
高橋名人なら余裕で弾けるかも?
調律師的には、高速連打にどこまで応えるピアノに調整出来るかが勝負どころであります。
今回は高橋名人が出演されてました。
私はインベーダー世代で小学生時代によく遊びました。
高橋名人は当時、有名人でしたが、実はゲームが下手だったとのことでした。
ただ秒間16連打というのはウソではないようで、なかなかマネできないように思います。
ラヴェルの「夜のガスパール」のスカルボに、dis音を約217回連続連打的な難曲があります。
親指、人差し指、中指の3本の指を使って弾くことが多いようですが、人差し指1本だけで弾く方もいらっしゃいます。
高橋名人なら余裕で弾けるかも?
調律師的には、高速連打にどこまで応えるピアノに調整出来るかが勝負どころであります。
プラシーボ効果
スターバックスのレギュラーコーヒーが好きで、仕事の前後に行ったりします。
注文するときはいつもマグカップにしてもらいます。
コーヒーは同じでもカップが違うと、気のせいかもしれませんが不思議と違った味がします。
ピアノも塗装の色で違って聞こえるかもしれません。
黒でも日本は艶出しが多いですが、海外では艶消しが好まれるとか、ピアノコンチェルトでは艶が光を反射してオケに対して眩しいので屋根は艶消しにすると良い、ということもあるようです。
白は洒落てていいようですが、ピアノが伴奏のときには目立ってしまい不向きかもしれません。
面白い話では、木目のピアノだと音が柔らかいという説もありますが、残念ながら私にはわかりません。
実際に科学的に違うかどうかより、そんな気がすると感じることが案外、大切かもしれないと思っております。
注文するときはいつもマグカップにしてもらいます。
コーヒーは同じでもカップが違うと、気のせいかもしれませんが不思議と違った味がします。
ピアノも塗装の色で違って聞こえるかもしれません。
黒でも日本は艶出しが多いですが、海外では艶消しが好まれるとか、ピアノコンチェルトでは艶が光を反射してオケに対して眩しいので屋根は艶消しにすると良い、ということもあるようです。
白は洒落てていいようですが、ピアノが伴奏のときには目立ってしまい不向きかもしれません。
面白い話では、木目のピアノだと音が柔らかいという説もありますが、残念ながら私にはわかりません。
実際に科学的に違うかどうかより、そんな気がすると感じることが案外、大切かもしれないと思っております。